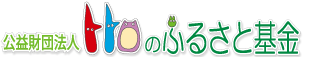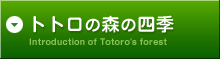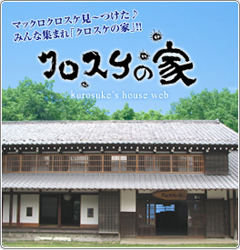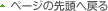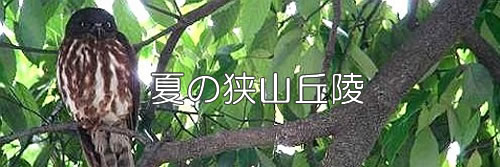
*** 里山と雑木林 季節の移ろい ***
6月、7月、8月の里山や雑木林を彩る、木々や野草の花を追ってみました。*** 2010年 6月 ~ 2010年 8月 ***
*** 葉 月 ***
*** 林縁に咲く草花 ***
雑木林の藪に白地の中心に赤色を付けた蔓草が蓋っています。草が悪臭を放つことから付けられた名前はヘクソカズラです。
見た目に綺麗な花、和名はヤイトバナと呼ぶそうです。

林内の木陰に、高さ1mの茎に白い花をつけているのはソクズ。
ニワトコの葉に似ていることからクサニワトコとも言われるそうです。
明るい陽射しの茶畑や垣根には蔓性のヤブガラシが繁茂します。
他の植物を蓋い、枯らしてしまうことからビンボウカズラと呼ばれます。

8月の暑い日差しを浴びて林縁に花を咲かせるクサギ。
秋には赤い星型のガクに青い実を付けます。
ヤブミョウガは、ミョウガの葉に似て、ヤブに生えるから付けられた名前。
5弁の綿毛の花を広げるのはガガイモ、これも蔓性の多年草です。

** 外来種 **
北アメリカ産の帰化植物で、ナスに似た花を付けるワルナスビ。
ヨウシュヤマゴボウも北アメリカ産です。

2010年 8月 狭山湖周辺の雑木林にて撮影
*** カラスウリ ***
秋に赤い実をつけるカラスウリ、その花は何時頃咲くのでしょうか。真夏の太陽が照りつける時期、林縁の草木や茶畑を蓋うように
絡みつき、青い大きな葉を一杯に広げます。

西の空が赤く焼け陽が傾く頃、日没を待ちきれず、蕾が膨らみ始めます。
陽が沈み宵闇が迫る頃から、スローモーションでも見ているかのように、
五弁の花ビラの先にレースの糸を絡ませたように真っ白な花が姿を現します。

18時40分 18時52分

19時05分
2010年8月3日 比良の丘にて撮影
*** 文 月 ***
雑木林の林縁にはオカトラノオが群落を作り、咲き揃いました。夏草刈りに、少しずつ生息域が狭まられています。

梅雨の季節、ホタルブクロが夏草の中に鐘のような形をした薄紫色の
花が下がっています。名前の由来は、蛍をこの中にとの言う説もあります。
アカマツの倒木も朽ち果て、次世代の雑木林を育てる温床に変身です。
コナラも、緑色のフカフカのコケの中、キノコに囲まれ育ち始めました。

ヤマユリも咲き始めましたが、雑木林内での株数も少なくなりつつあります。
下草刈り後に茎から菌が入り球根が犯されてしまうと言われています。
畦道では黄赤色のヤブカンゾウが群落を作り小道を飾ります。
この群落も2日後には、夏草刈りで消えてしまいました。

雑木林で目立つ白い花はヌルデ、秋には紅葉するウルシの仲間です。
夏の雑木林に、彩を添えるのは、夜になると細い葉を併せ垂れるネムの木です。
ぼんぼりの様な形をした雄しべの先は淡い赤紫に染め電気を灯したようです。。

2010年 7月上旬 狭山湖堤防下、堀内天満天神社周辺にて撮影
*** 大賀ハス 開花!! ***
西方十万億度にあるとされる極楽浄土、仏・菩薩が座るハスの花の台座、そのイメージを掻き立てるハスの花、丘陵の一角に位置する狭山不動尊で、
大賀ハスが開花しました。

大賀ハスの由来(表札に掲げられていた、“大賀ハスの由来”を転記)
昭和25年に中尊寺金色堂の御遺体調査に参加された故大賀一郎東大農学部教授が
藤原泰衡公の棺の中から数個の蓮の種子を発見されました大賀博士の没後中尊寺に
返還され宝物館に眠っていた蓮の種子を大賀博士門下の長島時子教授に依頼したところ
平成五年発芽に成功、平成十年七月二十九日開花した蓮は発見者の名前をとり大賀ハスと
名付けられました八百年を越えて咲く蓮のロマンに思いを馳せてください
狭山不動尊


2,010年7月上旬 狭山不動尊境内にて撮影
*** 水 無 月 ***

梅雨を前に、雑木林の一角を白く蓋っているのは、テイカカズラ、
五片のはなびらをプロペラ上に開き、秋には20cm長の豆のような
果実が開き、羽毛をつけた種子が風に舞います。
2010年 6月 上旬 上山口の八幡神社周辺にて撮影
雑木林に目だった白い花も終わり、桑の実は赤から黒に変わり
熟した事を知らせ、キイチゴはルビーのように赤く輝き

4月に白い花をつけたニワトコは、早くも赤い実を付け始めました。
初夏に日陰地に咲くドクダミ、濃緑食の葉に白い花弁のが映えます。

蔓性のテイカカズラ、五片の捩じれた白いプロペラが目に付きます。
雑木林の林縁の低木を蓋うスイカズラは、咲き始めの白い花は、
時間が経つとクリーム色に変化します。

2010年 6月上旬 みどりのトラスト2号地スポット2周辺にて撮影